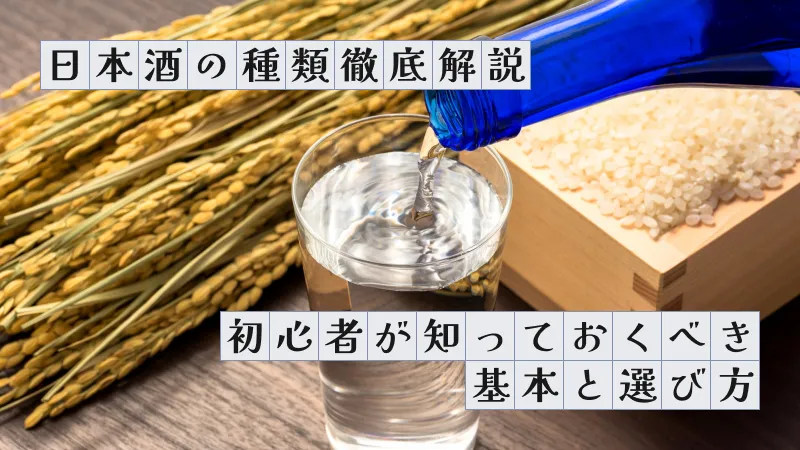
日本酒は日本が世界に誇る伝統的なお酒です。しかし、初めて日本酒に触れる方にとっては、その種類の多さや専門用語の難しさから、どれを選べばよいのか迷ってしまうことも多いでしょう。この記事では、日本酒の基本的な種類から初心者におすすめの銘柄まで、わかりやすく解説します。日本酒デビューを考えている方も、すでに飲み始めているけれどもっと詳しく知りたい方も、ぜひ参考にしてください。
目次
日本酒デビューの前に知っておきたいこと
日本酒の世界に足を踏み入れる前に、基本的な知識を身につけておくと、より楽しめるようになります。
初めに、一般的に「日本酒」と呼ばれるお酒は、法律上では「清酒」と呼ばれ、酒税法 第三条 第七号でアルコール分が1度以上22度未満かつ次のいずれかに当てはまるものと定められています。
- 米・米麹・水を原料として発酵させて、濾したもの。
- 米・米麹・水・清酒かす・その他政令で定められた物品を原料として発酵させて、濾したもの。但し、その他政令で定められた物品は米・米麹の重量の50%を超えないもの。
- 清酒に清酒かすを加えて、濾したもの。
さらに、「清酒の製法品質表示基準」という規定により、清酒の中でも原料の米に国内産米のみを使い、かつ、日本国内で製造された清酒に限り「日本酒」と表示してもよいことになっています。
日本酒の用語で知っておきたいのが「精米歩合」という概念です。これは、原料となる米をどれだけ削ったかを示す数値で、例えば精米歩合60%とは、玄米の外側40%を削り取り、残りの60%で酒を仕込むことを意味します。一般的に、精米歩合の%が低いほど(つまり米を多く削るほど)、雑味が少なくなり繊細な味わいになります。
日本酒の甘辛度合いを表す「日本酒度」も重要な指標です。プラスの値は辛口、マイナスの値は甘口を意味します。ただし、日本酒の辛口は、実際に辛味があるわけではなく、甘みが控えめでキレのいいシャープな味わいを指すことに注意が必要です。
また、日本酒を選ぶ際は「特定名称酒」というカテゴリーを知っておくと役立ちます。これは一定の基準を満たした高品質な日本酒を指し、品質の目安となります。次の項目で詳しく解説していきます。
日本酒の「特定名称酒」とは何か
「特定名称酒」とは、「清酒の製法品質表示基準」で定められた、日本酒の品質や製法に関する一定の基準を満たした酒に与えられる公式な名称です。極上・優良・高級等の品質が優れている印象を与える用語を使えない代わりに、一定の基準を満たしたお酒であることを明示できるというものです。
一般的には商品名に含まれていたりラベルに表示されていますが、特定名称を「表示できる」という規定のため、表示されていなくても問題はありません。そのため、特定名称を表示できる基準で造られていても、あえて使用している酒米や精米歩合にフォーカスして販売されているものもあります。
特定名称酒は大きく分けて「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」の3つのカテゴリーに分類されます。それぞれ使用する原料や精米歩合などの製造条件が異なり、味わいの特徴も変わってきます。
| カテゴリー | 条件 |
|---|---|
| 吟醸酒 | ・原料の米は精米歩合60%以下 ・原料は米・米こうじ・水、又はこれらと醸造アルコール ・固有の香味及び色沢が良好なもの |
| 純米酒 | ・原料は米・米こうじ・水 ・香味及び色沢が良好なもの |
| 本醸造酒 | ・原料の米は精米歩合70%以下 ・原料は米・米こうじ・醸造アルコール・水 ・香味及び色沢が良好なもの |
これらの特定名称酒は、各カテゴリー内でさらに精米歩合や製法によって細かく分類されます。初心者の方は、まずこの大きな分類を覚えておくと、日本酒選びの際に役立つでしょう。
次の項目からは、それぞれの各カテゴリーについてより詳しく見ていきましょう。
華やかな香りを堪能する吟醸酒
吟醸酒は、高度に精白した米を低温でゆっくりと発酵させて造られます。醸造アルコール(酒造りの過程で添加されるアルコール)を添加することで、雑味が少ないすっきりとした飲み口に仕上がります。特徴である「吟醸香」と呼ばれるフルーティーな香りは、リンゴやバナナ、メロンなどを思わせる華やかさがあり、日本酒の魅力を一層引き立てています。「吟醸酒」「大吟醸酒」がこのカテゴリーに含まれます。
吟醸酒は、前述した通り、精米歩合60%以下の米を使用して造られます。大吟醸ほど贅沢ではないものの、十分にフルーティーな香りと滑らかな口当たりを持ち、親しみやすい価格帯で高級感のある日本酒を楽しみたい方におすすめです。冷酒から常温で楽しむのが一般的です。
大吟醸酒は、さらに精米を行い、精米歩合50%以下の米を使用して造られます。非常に繊細で上品な味わいが特徴で、日本酒の最高峰とも言われています。冷酒で飲むことで、その繊細な香りと味わいを最大限に楽しむことができます。
米の旨味を堪能する純米酒
純米酒は、その名の通り米・米麹・水のみを原料とし、醸造アルコールを一切添加していないのが最大の特徴です。そのため、米本来の旨味や複雑な味わいを楽しむことができます。温度によって風味や味わいが大きく変わるので、冷酒から燗酒まで幅広く楽しめます。「純米酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」「特別純米酒」がこのカテゴリーに含まれます。
純米酒は、前述した通り、特に精米歩合の規定はないものの、一般的には精米歩合70%前後で造られます。米の旨味をしっかりと感じられ、米の香りにコクや深みのあるまろやかな味わいが特徴です。
純米吟醸酒は、吟醸酒と同様に精米歩合60%以下の米を使用して低温でゆっくりと発酵させて造られます。純米大吟醸ほどではないものの、フルーティーな香りに滑らかな口当たりです。甘みと酸味のバランスがよく取れており、純米酒よりも米の風味が控えめな上品で洗練された味わいが特徴です。
純米大吟醸酒は、大吟醸酒と同様に精米歩合50%以下の米を使用して低温でゆっくりと発酵させて造られます。非常に繊細で芳醇な香りと味わいで、純米酒の中でも最高級とされる種類です。フルーティーで華やかな香りと共に米の旨味がふわりと広がり、後味はすっきりとしているのが特徴です。
特別純米酒は、純米酒の基準を満たした上で、「使用原材料もしくは製造方法に特別な工夫を凝らしている」かつ「工夫を凝らしている箇所に精米歩合が含まれる場合は精米歩合60%以下の米を使用している」を満たしたものを指します。製造方法自体に規定はないため、味わいは多岐にわたりますが、「特別」の名に恥じない味わい深さがあります。
万人受けの本醸造酒
本醸造酒は、香りが控えめですっきりとした飲み口と軽やかな味わいが特徴です。バランスの良さと飲みやすさから、多くの人に親しまれている種類です。冷酒から燗酒まで、温度による味の変化を楽しめます。「本醸造酒」「特別本醸造酒」がこのカテゴリーに含まれます。
本醸造酒は、前述した通り、精米歩合70%以下の米を使用して造られます。純米酒や吟醸酒ほど贅沢な原料ではありませんが、すっきりとした味わいと程よい香りを持ち、日常的に楽しむ日本酒として人気があります。
特別本醸造酒は、本醸造酒の基準を満たした上で、「使用原材料もしくは製造方法に特別な工夫を凝らしている」かつ「工夫を凝らしている箇所に精米歩合が含まれる場合は精米歩合60%以下の米を使用している」を満たしたものを指します。製造方法自体に規定はないため、味わいは多岐にわたりますが、本醸造より一段上の品質を持ち、より繊細な味わいが楽しめます。
侮れない普通酒
特定名称酒の分類に入らない日本酒は「普通酒」と呼ばれています。「普通」という名前から品質が劣ると思われがちですが、決してそうではありません。
普通酒は長い歴史の中で日本人の食卓を支えてきた伝統的な日本酒です。地域ごとの気候や水質に合わせた製法で造られているため、その土地ならではの個性を持っています。また、醸造アルコールの添加により雑味が抑えられ、すっきりとした飲み口になっているのが特徴です。
普通酒は価格も比較的リーズナブルなため、日常的に気軽に楽しめるのも魅力です。また、料理に使用する料理酒としても重宝されています。煮物や鍋物に少量加えることで、食材の臭みを消し、旨味を引き立てる効果があります。
侮れないのはその多様性です。同じ普通酒でも、蔵元によって全く異なる味わいを持っており、中には特定名称酒に引けを取らない秀逸な普通酒も数多く存在します。
初心者におすすめの銘柄ガイド
日本酒の世界は広く、初めての方にとっては何を選べばよいか迷ってしまうことも多いでしょう。ここでは、初心者の方におすすめの銘柄をいくつか紹介します。それぞれ特徴が異なりますので、自分の好みに合いそうなものから試してみてください。
まず、吟醸酒では新潟県の朝日酒造による「久保田 千寿」がおすすめです。バランスの良さで知られ、辛口のすっきりとした飲み口と強すぎず程よい吟醸香が魅力です。冷酒で楽しむのがおすすめですが、少し温めて飲んでも美味しくいただけます。
次に、純米酒では兵庫県の白鶴酒造による「特撰 白鶴 特別純米酒 山田錦」がおすすめです。やや辛口であるものの、原料である山田錦由来の米のまろやかな甘みとコク深い味わいが魅力です。冷酒だと爽やかに、常温だと米の旨味をしっかり楽しめます。
本醸造では兵庫県の菊正宗酒造による「上撰 生酛 本醸造」がおすすめです。自然な乳酸菌を使う、生酛仕込みという伝統的な製法で造られています。辛口でキレのあるすっきりとした味わいが特徴です。常温〜ぬる燗がまろやかでおすすめです。
普通酒では京都府の月桂冠による「月桂冠 つき」がおすすめです。やや甘口のフルーティーで軽やかな飲み心地が特徴です。料理を邪魔しない味わいなので、普段の食事とも気軽に合わせられます。
また、女性や若い世代に人気なのが京都府の宝酒造によるスパークリング日本酒「澪」です。爽やかな炭酸と甘みのバランスが絶妙で、日本酒が苦手だという方でも楽しめる、新しいタイプの日本酒といえます。
これらはほんの一例ですが、日本酒デビューの第一歩として試してみる価値のある銘柄です。また、最近では小瓶(180ml〜300ml)で販売されている日本酒も多いので、いろいろな種類を少しずつ試してみるのも良い方法です。
自分好みの日本酒を見つけるコツ
日本酒の世界は実に多様で、自分好みの一本を見つけるのは探求の旅のようなものです。ここでは、その旅をより楽しく、効率的にするためのコツをご紹介します。
まず大切なのは、自分の好みを知ることです。甘口と辛口、フルーティーなものと米の旨味を感じるもの、軽快なものとコクのあるもの、それぞれどのような特徴に惹かれるかを意識しながら飲んでみましょう。最初は「美味しい/美味しくない」という単純な感想でも構いません。徐々に自分の好みのパターンが見えてくるはずです。
次に、日本酒の温度にも注目してみましょう。同じ日本酒でも、冷やして飲む(5℃前後)、常温で飲む(室温)、温めて飲む(40〜45℃)で、まったく異なる味わいを楽しめます。自分が好きな銘柄でも、温度を変えるだけで新たな発見があるかもしれません。
また、酒販店や飲食店のスタッフに相談するのも効果的です。「甘めのものが好き」「すっきりした後味のものを探している」など、自分の好みを伝えると、適切な銘柄を紹介してもらえることが多いです。特に専門店では、試飲ができる場合もありますので、積極的に活用しましょう。
最後に、日本酒の情報を記録しておくことをおすすめします。スマートフォンのメモアプリやSNSに、飲んだ日本酒の銘柄や感想、どんな場面で飲んだかなどを残しておくと、自分の好みの傾向が見えてくるだけでなく、後から振り返る楽しみもあります。
日本酒との出会いは一期一会。様々な銘柄との出会いを楽しみながら、あなただけのお気に入りを見つけてください。



